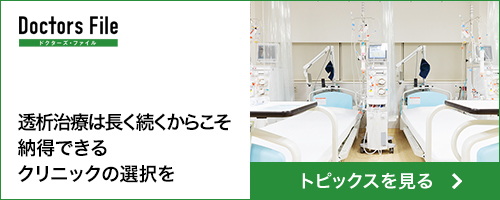(腎性)副甲状腺機能亢進症
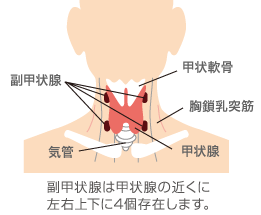
副甲状腺自体に原因があるのではなく、くる病やビタミンD欠乏症、慢性腎不全などが原因で副甲状腺ホルモンが過剰に分泌され、血液中のカルシウム濃度が必要以上に高くなる病気を二次性(続発性)副甲状腺機能亢進症といいます。
二次性(続発性)副甲状腺機能亢進症の代表的な原因に、腎性副甲状腺機能亢進症があります。
病態
慢性腎不全になると、腎臓でのリン(P)の排泄およびビタミンD3の活性化ができなくなります。また活性化ビタミンD3が低下すると、腸管からのCaの吸収が低下します。
つまり、慢性腎不全の人は血液中のカルシウム(Ca)が低下し、Pが上昇するわけですが、これらの状態は副甲状腺を刺激し、副甲状腺ホルモン(PTH)の分泌を促します。そして長期間刺激され続けた副甲状腺は腫大し、やがて血液中Caの値に関係なく PTHが過剰に分泌され、血液中のCa濃度が必要以上に高くなる状態となります。
二次性副甲状腺機能亢進の発生機序
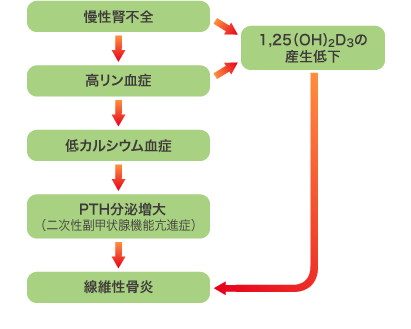
症状
PTHの過剰な分泌は、骨から血液中へのCa吸収を引き起こし、骨がもろくなる「線維性骨炎」となり、骨痛や骨変形・病的骨折などの原因となります。
また、血液中のCa濃度が高くなると、さまざまな場所へCa沈着(異所性石灰化)し、動脈硬化や弁膜症・関節炎などを引き起こします。
検査
2006年に発表された日本透析医学会の「透析患者における二次性副甲状腺機能亢進症治療ガイドライン」 は2012年に改定された「慢性腎臓病に伴う骨ミネラル代謝異常(CKD-MBD)の診療ガイドライン」になり、生命予後(命に関係する)因子である血中リン(以下P)濃度の管理を第一に,ガイドラインに基づいた適正な管理を行い,慢性腎臓病(CKD)患者の予後が改善される事への期待を述べたものになりました。
治療の基本は、まず血清リン濃度が適正値(管理目標値 3.5~6.0mg/dl)にコントロールされていることを最優先し、その後 血清カルシウム濃度を適正値(管理目標値:8.4~10.0mg/dl)※に管理することです。
※アルブミン(Alb)が低い方(血液中アルブミン4.0g/dL未満)は血液中Caを補正する必要があります。
補正Ca値 = 血液中Ca値 +(4-血清アルブミン値)
現在、当院ではwhole PTH(透析者の目標値80〜110pg/ml)を採用しております。
(whole PTH)×1.7 = i-PTH
なぜ現在はwhole PTHが主流になったのか? 血液検査の項目で紹介します。